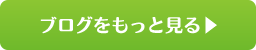肩こり
肩こりとは?
肩こりとは正式な病名ではなく、僧帽筋という肩の盛り上がっている筋肉の過剰な緊張により痛みや不快感を生じた状態を言います。
僧帽筋は首から始まる筋肉なので、首に同様の痛みや不快感を生じる事もあります。

肩こりはなぜ起きる?
日本人の国民病とも言われているのには理由があります。
日本人は欧米の人と比較すると肩幅が狭い為、腕の重みがダイレクトに首や肩に掛かってしまうのです。
それに加えてPCやスマートフォンの急速な普及により猫背の人が増えてきています。
肩こりを抱えている方の多くは猫背でもお悩みではないでしょうか?
猫背になると肩が凝るのはなぜ?
猫背になると肩が内巻状態になってしまう事が原因なのです。
肩が内に巻くという事は、後ろの僧帽筋が引っ張られてしまい緊張してしまいます。

肩こりを改善する為には?
肩こりを治そうとする時に、症状のある僧帽筋ばかりに注目してしまいがちですが、猫背で説明したように真の原因は肩を内巻にしてしまう大胸筋や腋の肩甲下筋といった筋肉をほぐす事がポイントです。
肩こりはあくまで結果であり、なぜこったのかという過程の部分を改善する必要があるのです。
肩こりの患者様にお勧めの施術
あさひろ鍼灸整骨院の肩こり治療
①強い痛みがひどい肩こりや頭痛を伴う場合
痛みがひどい場合、特に頭痛を伴う場合は鍼治療を行います。
即効性があるので、眠れない痛みや疼くような痛みを感じている方はご相談ください。
②慢性的な肩こりには
症状のある肩の治療はもちろんですが、根本的な原因となる姿勢の改善を目的とした背骨・骨盤矯正を行っていきます。
姿勢が正しければ、現在より筋肉の緊張は無く力の抜けた状態となります。
③イライラやのぼせを伴う肩こりには
こちらは鍼や灸を行い 体内の熱のバランスを取る治療を行います。
更年期の女性の肩こりはこのケースが多く見られます。