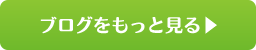眼精疲労
眼精疲労とは?
眼精疲労とは、目を使う仕事などを続けることにより、目の痛み、目のかすみ、充血、まぶしさなど目の症状に加え、頭痛、肩こり、吐き気などの全身に症状が出てきて、休息や睡眠をとってもしっかり回復しない状態をさします。
眼精疲労をもたらす要因としては、度の合わない視力矯正を行なっていたり、近業作業を長時間行った場合です。その他緑内障、白内障、ドライアイで出たり、全身疾患に伴うもの、心因性のもの、環境によるものなど眼精疲労をおこす要因は多岐にわたります。
あさひろでの眼精疲労治療
あさひろ鍼灸整骨院での眼精疲労治療
当院で治療可能な眼精疲労は主に近業作業による眼精疲労となります。
眼精疲労に特化したメニュー
【眼精疲労整体】
目の周りの筋肉、頭部を動かすだけでなく眼球を動かす際にも働く後頭下筋群をほぐすことで、眼精疲労・頭痛・頭重感・首コリを解消していくメニューです。
【眼精疲労鍼】
眼精疲労と同様で、目の周りの筋肉、後頭下筋、頭周囲の筋肉に直接鍼を打つことで、緊張を取ります。